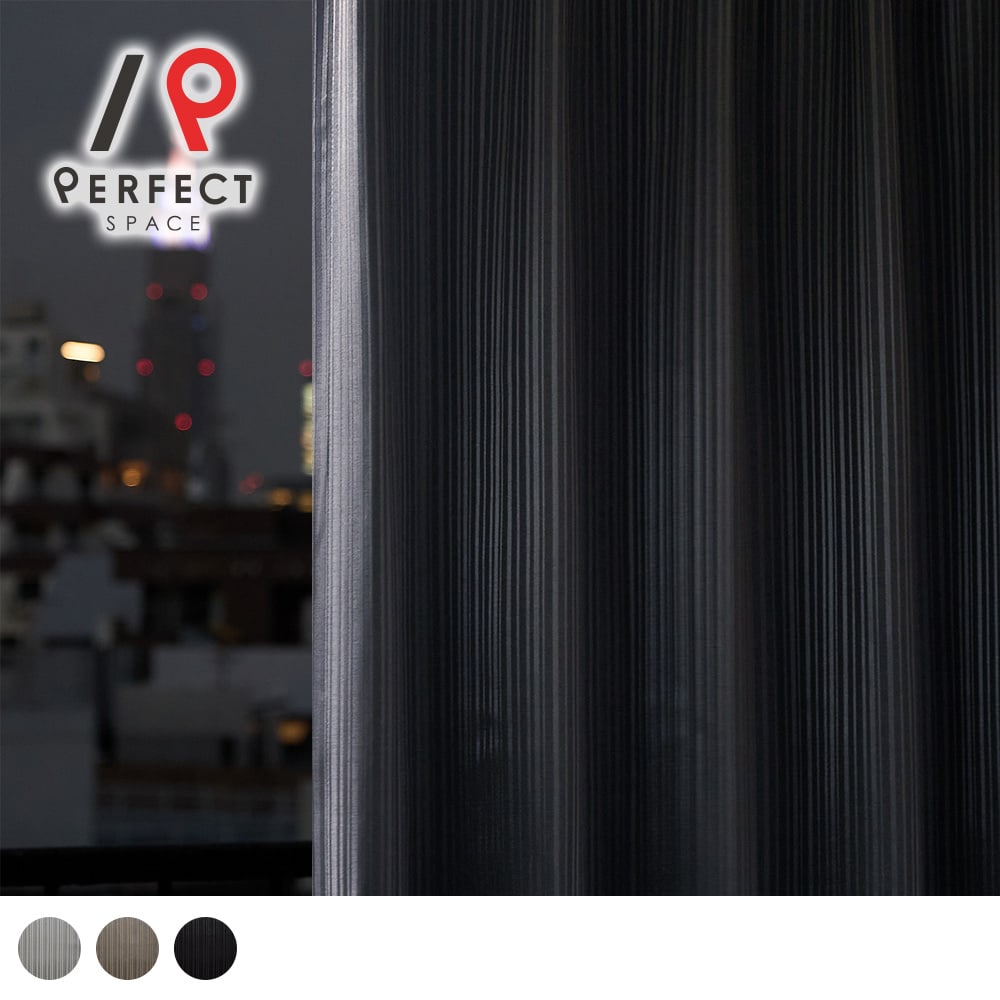Contents
80代夫婦の相続対策:息子への相続回避と配偶者への財産承継
80代のご夫婦が、ご子息への相続を避け、配偶者間での円滑な財産承継を希望されているとのこと。関東の戸建て、関西のマンション、そして1500万円の預金という資産をお持ちで、不動産の名義はご主人名義とのことです。ご子息が法科卒であることも考慮すると、相続手続きにおける法的知識は高いと推測できます。
このケースでは、相続発生前に適切な対策を行うことが重要です。具体的には、以下の2つの方法が考えられます。
1. 生前贈与
生前贈与とは、相続が発生する前に、財産を贈与することです。この方法では、贈与税が発生する可能性がありますが、相続税よりも税率が低い場合が多く、相続手続きの煩雑さを軽減できます。
- メリット:相続税対策として有効、相続手続きが簡素化される。
- デメリット:贈与税が発生する可能性がある、贈与額によっては税金が高額になる可能性がある。
生前贈与を行う場合、贈与税の計算には「贈与税の基礎控除」が適用されます。年間110万円までは非課税です。ご夫婦で220万円まで贈与できます。また、暦年贈与を活用すれば、毎年一定額を贈与することで税負担を軽減できます。
ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)
さらに、ご子息が法科卒であることを考慮すると、贈与契約の内容を明確に記した書面を作成し、贈与の意思表示を明確にすることが重要です。トラブルを防ぐためにも、弁護士に相談して契約書を作成することをお勧めします。
2. 相続時における遺言書の作成
遺言書を作成することで、相続財産の分配方法を自由に決定できます。具体的には、ご主人から奥様への遺贈を指定する遺言書を作成することで、ご子息への相続を回避できます。
- メリット:相続人の意思を尊重できる、相続争いを予防できる。
- デメリット:遺言書の作成には費用がかかる、遺言内容によっては相続人から争われる可能性がある。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。公正証書遺言は、公証役場で作成されるため法的効力が強く、紛争リスクが低いのが特徴です。費用は、公証役場の手数料と、弁護士への相談費用(任意)が必要になります。費用は、遺言の内容や弁護士への依頼の有無によって異なりますが、数万円から数十万円程度と想定されます。
不動産の名義変更と共有名義について
質問にある「不動産を共有名義にするのが先ですか?それとも公正証書が先ですか?」という点ですが、どちらが先という順番はありません。状況に応じて最適な方法を選択する必要があります。
共有名義にすることで、ご夫婦で所有権を共有することになります。しかし、これは相続対策としては必ずしも有効とは限りません。共有名義にすることで、相続手続きが複雑になる可能性もあります。
遺言書と併用することで、効果を発揮するケースもあります。例えば、遺言書で「亡くなった方の持分は配偶者に相続させる」と指定し、生前に共有名義にしておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。
専門家への相談が重要
相続問題は複雑で、専門的な知識が必要です。特に、ご子息が法科卒であるとはいえ、ご夫婦の意思を確実に反映させ、相続トラブルを回避するためには、税理士や弁護士などの専門家への相談が不可欠です。
専門家への相談費用は、相談内容や弁護士・税理士の事務所によって異なりますが、数万円から数十万円程度を見込んでおきましょう。
まとめ:具体的なステップと費用感
1. **専門家への相談(税理士・弁護士):**まずは、ご夫婦の状況を説明し、最適な相続対策を検討しましょう。費用:数万円~数十万円。
2. **生前贈与または遺言書の作成:**専門家のアドバイスに基づき、生前贈与もしくは遺言書を作成します。費用:生前贈与は贈与税、遺言書は公証役場手数料と弁護士費用(任意)。
3. **不動産の名義変更(必要に応じて):**共有名義への変更や、遺言書の内容に基づいた名義変更を行います。費用:登録免許税など。
上記費用はあくまで目安です。具体的な費用は、資産規模や専門家の選定によって変動します。