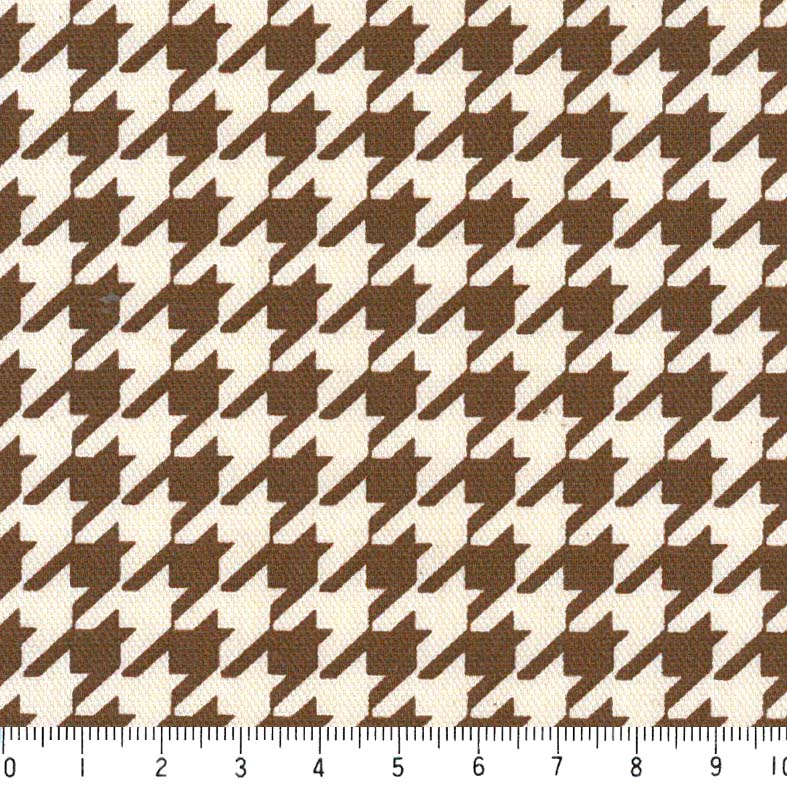Contents
床鳴りの原因と大工さんの説明の妥当性
2階畳をフローリングに張替え後、床鳴りが発生しているとのこと、ご心配ですね。大工さんの説明「フローリングは畳に比べて厚みが少ないので多少きしみはできる」は、完全に正しいとは言えません。確かに、畳に比べてフローリングは薄いため、下地からの振動が伝わりやすく、床鳴りが発生しやすくなる可能性はあります。しかし、「多少のきしみは仕方ない」と片付けるのは、適切な施工が行われていない可能性を示唆しています。
床鳴りの主な原因は、以下の通りです。
- 下地材の不備:古いベニヤ板の上から直接根太を施工したとのことですが、古いベニヤ板の状態が悪かったり、十分な強度が確保できていない場合、床鳴りの原因になります。ベニヤ板の腐食や剥がれ、釘の緩みなどが考えられます。
- 根太の間隔が広い:300mm間隔は、フローリング下地としてはやや広い可能性があります。間隔が広いと、コンパネやフローリングにたわみが生じ、床鳴りが発生しやすくなります。理想的な間隔は、使用する材料やフローリングの種類によって異なりますが、通常は150~200mm程度です。
- 根太とコンパネの固定不良:根太とコンパネの固定が不十分だと、コンパネが動き、床鳴りが発生します。十分な数の釘やビスでしっかりと固定する必要があります。
- コンパネの品質:コンパネの品質が低いと、強度が不足し、床鳴りの原因となります。JIS規格に適合したコンパネを使用することが重要です。
- 施工ミス:根太の水平がとれていない、コンパネの継ぎ目が適切に処理されていないなど、施工ミスも床鳴りの原因となります。
1階天井からの補強:効果と方法
大工さんが提案している「1階の天井から角材で補強する」方法ですが、これは効果がある可能性はありますが、根本的な解決策ではありません。この方法は、2階の床を支える梁に角材を追加することで、床のたわみを抑制し、床鳴りを軽減する効果が期待できます。しかし、原因が下地材の不備や固定不良にある場合は、この方法だけでは完全に解決できない可能性があります。
1階と2階からの補強の違い
1階天井から補強する場合、既存の梁に角材を追加して補強します。一方、2階から補強する場合、床下地自体を補強することになります。床鳴りの原因が下地にある場合は、2階から直接補強する方が効果的です。しかし、1階天井からの補強は、床下へのアクセスが困難な場合や、大規模な改修が難しい場合に有効な手段となります。
ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)
正しいフローリングの下地施工
正しいフローリングの下地施工は、床鳴りを防ぐ上で非常に重要です。以下に、適切な手順を示します。
1. 下地調整
- 既存のベニヤ板の状態を確認し、腐食や剥がれ、釘の緩みなどがあれば、取り除いて新しいベニヤ板を敷設する必要があります。状態が良い場合は、そのまま使用することも可能ですが、その場合はしっかりと固定し直す必要があります。
- 床面を清掃し、水平を調整します。必要に応じて、下地調整材を使用します。
2. 根太の施工
- 根太は、150~200mm間隔で施工します。使用するフローリングの種類や厚さによって適切な間隔は異なりますので、専門家に相談することをお勧めします。
- 根太は、水平器を使用して水平に施工します。根太と既存の床との間に隙間が生じないように注意します。
- 根太は、十分な強度を持つ木材を使用し、適切な長さの釘やビスでしっかりと固定します。
3. コンパネの施工
- 根太の上にコンパネを敷設します。コンパネは、JIS規格に適合した品質の良いものを選びます。
- コンパネは、釘やビスでしっかりと根太に固定します。継ぎ目は、適切に処理します。
4. 防湿シートの施工
- コンパネの上に防湿シートを敷設します。防湿シートは、湿気による床鳴りや腐食を防ぐために重要です。
5. フローリングの施工
- 防湿シートの上にフローリングを施工します。フローリングの施工方法は、使用するフローリングの種類によって異なりますので、取扱説明書をよく読んで施工してください。
専門家の意見とアドバイス
今回のケースでは、大工さんの説明に納得できない部分があります。床鳴りは、施工不良の可能性が高いです。専門の業者に相談し、床鳴りの原因を特定し、適切な補修工事を行うことを強くお勧めします。安価な工事で済ませようとすると、後々大きな問題に発展する可能性があります。
信頼できる業者選びのポイント
- 複数の業者に見積もりを依頼する
- 施工実績や評判を確認する
- 保証内容を確認する
- 契約内容をしっかりと確認する
床鳴りの原因を特定し、適切な補修を行うことで、快適な住空間を取り戻せるはずです。