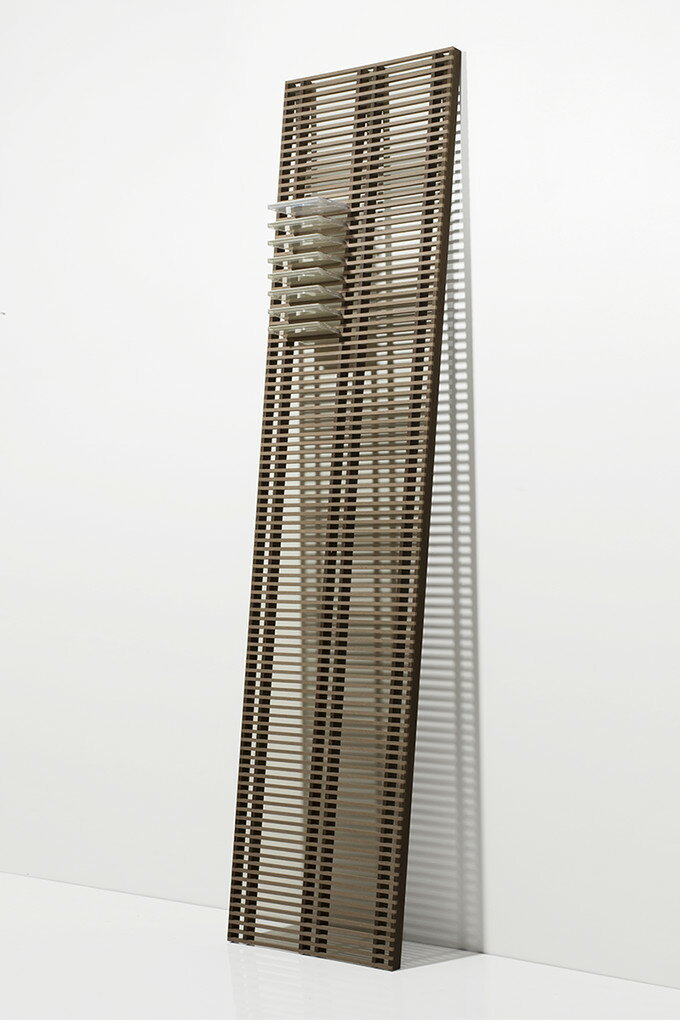Contents
現状把握と目標設定から始めよう
まず、現状を正確に把握し、具体的な目標を設定することが大切です。 ご自身の状況を丁寧に説明していただきありがとうございます。現状は、時間がない中で家事が追いつかず、物が溢れてしまっている状態ですね。 まずは、「どんな状態にしたいか」を具体的にイメージしましょう。「ソファーに物がなく、落ち着いて過ごせるリビング」「床に物がなく、子供が安全に遊べる空間」「来客時にも恥ずかしくないキッチン」など、具体的な目標を設定することで、モチベーションを維持しやすくなります。
ステップ1:捨てる!断捨離で空間を作る
収納家具を増やす前に、まずは不要な物を捨てることから始めましょう。 「要るもの」「要らないもの」「迷うもの」の3つに分類し、まずは「要らないもの」を処分します。
捨てる基準を明確に
捨てる基準を明確にすることで、迷いを減らすことができます。例えば、
- 1年以上使っていないもの
- 同じようなものが複数あるもの
- 壊れているもの
- もう着ない服
- 子供が使わなくなったおもちゃ
などを基準にすると、判断しやすくなります。 「いつか使うかもしれない」と迷うものについては、写真に撮って記録しておけば、必要になった時に探しやすくなります。
ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)
捨てる方法
不用品は、ゴミとして処分する、リサイクルショップに売る、フリマアプリで売る、寄付するなど、様々な方法があります。 時間がない場合は、粗大ゴミ回収サービスを利用するのも良いでしょう。
ステップ2:収納を見直す
不要な物を処分したら、次は収納を見直します。 現状では、収納場所が決まっているものの、ダンボールに入れたままになっているものや、クローゼットがいっぱいの状態です。
収納場所の整理
まずは、それぞれの収納場所にある物を全て出して、中身を確認します。 不要な物は処分し、残った物を種類別に分類します。 そして、使用頻度が高いものは取り出しやすい場所に、低いものは奥に収納するようにしましょう。
収納用品を活用する
収納用品を活用することで、収納効率を上げることができます。 例えば、
- 引き出しケース:細かい物を整理するのに便利
- 収納ボックス:統一感を持たせることができ、見た目もスッキリする
- ラック:空間を有効活用できる
- ファイルボックス:書類を整理するのに便利
などがあります。 100円ショップでも様々な収納用品が手に入るので、まずは手軽に試してみるのも良いでしょう。
クローゼットの整理
クローゼットがいっぱいの場合は、服を季節別に分けて収納し、オフシーズンの服は圧縮袋に入れて収納すると、スペースを節約できます。 また、ハンガーを統一することで、見た目もスッキリします。
ステップ3:習慣化と維持
整理整頓は、一度片付ければ終わりではありません。 継続して行うことが大切です。 そのためには、
- 毎日5分間の片付け:寝る前に5分間だけ片付ける習慣をつける
- 週末の大掃除:週末に時間をとって、徹底的に掃除をする
- 家族で協力する:家族みんなで片付けをする習慣を作る
など、無理のない範囲で継続できる習慣を作ることが重要です。
ステップ4:専門家の力を借りる
どうしても自分だけでは難しい場合は、整理収納アドバイザーなどの専門家の力を借りるのも良いでしょう。 専門家は、個々の状況に合わせたアドバイスをしてくれるので、効率的に片付けを進めることができます。
具体的な収納家具の提案
収納家具を選ぶ際には、部屋のサイズや収納したい物に合わせて選ぶことが大切です。
リビング
ソファーに物が置かれないように、収納付きソファーや、サイドテーブルに収納バスケットを置くなど工夫してみましょう。 おもちゃ収納には、子供にも使いやすい低い収納ボックスがおすすめです。
寝室
寝室の床に物が散乱しているとのことですので、ベッドサイドテーブルやチェストなどを活用し、収納スペースを増やすことを検討しましょう。 季節外の衣類は、圧縮袋に入れて収納することで、スペースを節約できます。
子供部屋(物置)
子供部屋は、お子さんの成長に合わせて変化していく場所です。 まずは、不要な物を処分し、残った物を整理して収納しましょう。 収納ボックスやシェルフなどを活用し、お子さんが自分で片付けやすいように工夫することが大切です。
キッチン
ダンボールに入れたままの物は、収納ボックスに移し替えることで、見た目もスッキリします。 ラベルを貼ることで、どこに何が収納されているか分かりやすくなります。
まとめ
整理収納は、時間と労力を要する作業ですが、継続することで、快適な生活空間を作ることができます。 まずは小さなことから始め、少しずつ習慣化していくことが大切です。 ご自身のペースで、焦らず取り組んでいきましょう。 そして、ご主人にも、現状と目標を共有し、協力体制を築くことも重要です。 小さな協力でも、大きな助けになります。