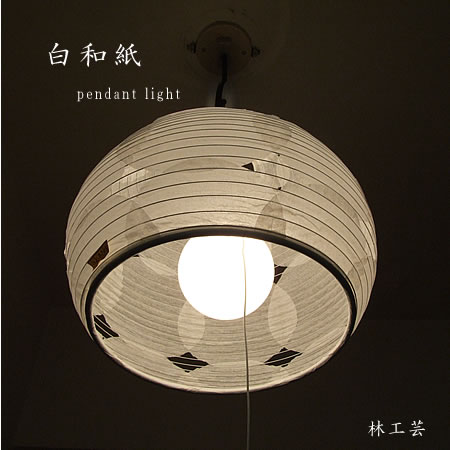Contents
認知症と異食行為:その危険性と対処法
認知症の進行に伴い、異食行為(本来食べられないものを食べてしまう行為)が現れることは珍しくありません。ご自身の母親がトイレットペーパーを食べたという事例は、残念ながら決して稀なケースではありません。 ご主治医の「窒息死というのはよくあること」という発言は、決して大げさではありません。トイレットペーパーのような繊維質のものは、消化されにくく、喉に詰まれば窒息死につながる危険性があります。一方、ヘルパーの「異食行為で死ぬことはない」という発言は、専門家の見解としては不適切です。
異食行為の原因は、認知症による脳機能の低下、感覚の鈍麻、空腹感や渇望感、または単なる好奇心など、様々な要因が考えられます。 重要なのは、異食行為そのものよりも、それが引き起こす可能性のある危険性を理解することです。窒息の危険性に加え、誤嚥性肺炎、腸閉塞、消化器系の障害なども起こりうるため、細心の注意が必要です。
異食行為による窒息死のリスク:具体的な危険性
- 窒息:トイレットペーパー、紙おむつ、布などの繊維質のものは、喉に詰まりやすく、窒息死の直接的な原因となります。特に、小さく丸めて飲み込む場合、気管を完全に塞いでしまう可能性が高まります。
- 誤嚥性肺炎:異物を誤って気管支に入れた場合、肺炎を引き起こす可能性があります。特に高齢者は免疫力が低下しているため、重症化のリスクが高まります。
- 腸閉塞:消化できない異物を大量に摂取した場合、腸閉塞を起こす可能性があります。激しい腹痛や嘔吐、便秘などを引き起こし、命に関わる事態にもなりかねません。
- 消化器系の障害:異物の種類によっては、胃や腸に傷をつけたり、炎症を引き起こしたりする可能性があります。
施設での安全対策とご家族の役割
ご家族ができることは、施設と連携して安全対策を徹底することです。
施設への要望と確認事項
* 危険物の撤去:トイレットペーパー、紙おむつ、その他危険なものは、手の届かない場所に保管してもらうよう施設に強く要望しましょう。
* 監視体制の強化:異食行為の頻度や時間帯を把握し、その時間帯に職員による監視体制を強化してもらうよう依頼しましょう。
* ヘルパーへの教育:異食行為の危険性に関する教育を、施設のスタッフ、特にヘルパーに対して行ってもらうよう働きかけましょう。
* 記録の確認:異食行為の記録を定期的に確認し、状況の変化を把握しましょう。
* 緊急時の対応:緊急時の対応手順や連絡体制を事前に確認しておきましょう。
ご自宅での安全対策(もし一時的に母を自宅に迎える場合)
* 危険物の撤去:自宅内から危険物を徹底的に排除しましょう。
* 家具の配置:転倒や衝突による怪我を防ぐため、家具の配置を見直しましょう。
* 床材:滑りやすい床材は、転倒リスクを高めます。滑りにくい素材のマットなどを敷くことを検討しましょう。
* 照明:十分な明るさを確保しましょう。暗い場所では、転倒リスクが高まります。
* 手すり:必要な場所に手すりを設置しましょう。
インテリアの観点からの安全対策
インテリアの観点からも、安全性を高める工夫ができます。
* 家具の角を保護する:角のある家具には、クッション材などを貼り付けて、怪我を防ぎましょう。
* 床の色:床の色は、視覚的な情報として重要です。コントラストがはっきりした色を選ぶことで、転倒リスクを軽減できます。例えば、ベージュの床に濃い色の家具を置くことで、家具の存在が明確になります。
* 照明:柔らかく、目に優しい照明を選びましょう。
* 素材:自然素材を使った家具やインテリアは、安心感を与え、落ち着きのある空間を演出します。
専門家の意見と心の準備
ご主治医の意見を参考に、現実的な心の準備をしておきましょう。異食行為は、認知症の症状の一つであり、完全に止めることは難しい場合があります。大切なのは、ご自身の心身の健康も維持しながら、母親の安全を確保することです。
まとめ
認知症患者の異食行為は、窒息死などの危険性を伴う深刻な問題です。施設と連携し、安全対策を徹底することはもちろん、ご自身の心身の健康も大切にしてください。 インテリアの工夫も、安全で安心できる環境を作る上で役立ちます。 悲観的になるのではなく、できる限りの対策を行い、穏やかな時間を過ごせるよう努めましょう。