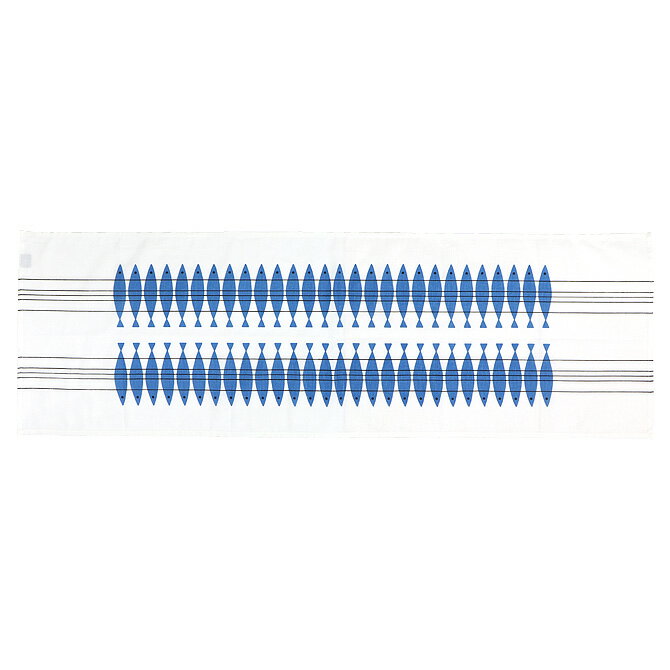Contents
認知症の母と病院受診、医師の対応への対処法
ご自身の辛い経験、心よりお見舞い申し上げます。認知症の患者を介護するご家族にとって、医療機関とのコミュニケーションは非常に重要であり、今回の出来事は大きなストレスになったことと思います。 医師の対応に不満を感じ、今後の受診に不安を抱えていることでしょう。 しかし、この経験を活かし、より良い医療環境を選択し、母さんのケアを継続していくために、具体的な対策を検討していきましょう。
1. 医師とのコミュニケーションの改善策
まず、今回の出来事から学ぶべき点は、医師とのコミュニケーション方法です。 認知症の患者を診察する際には、患者本人の言葉だけでなく、介護者であるご自身の説明も非常に重要になります。
- 事前にメモを作成する: 母の症状(排尿困難、腹痛など)、服用している薬、薬の副作用と思われる症状などを箇条書きでメモしておきましょう。 これにより、医師への説明がスムーズになり、重要な情報が抜け落ちるのを防ぎます。
- 具体的な症状を伝える: 「気分が悪い」といった曖昧な表現ではなく、「吐き気がある」「嘔吐した」「食欲がない」など、具体的な症状を伝えましょう。 いつから症状が出始めたか、症状の頻度や程度なども詳細に伝えれば、医師も的確な判断ができます。
- 穏やかなトーンで話す: 感情的な言葉遣いは、医師との良好な関係を築く上で障害となります。 冷静に、事実を淡々と伝えることを心がけましょう。 もし感情的になりそうになったら、一度深呼吸をして落ち着きましょう。
- 通訳者・サポート者の同伴: 必要であれば、ご家族や友人、介護支援専門員などに同行してもらい、医師とのコミュニケーションをサポートしてもらいましょう。 第三者がいることで、医師の言葉も客観的に理解しやすくなります。
- 医療機関へのフィードバック: 医療機関には、患者からの意見や苦情を受け付ける窓口があるはずです。 今回の出来事を冷静に伝え、改善を求めることも可能です。 ただし、感情的な言葉ではなく、事実を基に具体的な改善策を提案するようにしましょう。
2. 適切な医療機関の選び方
今回の経験を踏まえ、より適切な医療機関を選ぶことが重要です。 認知症患者に理解のある医療機関を選ぶために、以下の点を考慮しましょう。
- 専門医の有無: 認知症や泌尿器科の専門医がいる医療機関を選ぶことが重要です。 専門医は、認知症患者特有の症状や問題に精通しており、適切な対応をしてくれる可能性が高いです。
- 患者の声への対応: 医療機関のホームページや口コミサイトなどを参考に、患者の声への対応が丁寧な医療機関を選びましょう。 患者を尊重し、丁寧な説明をしてくれる医療機関を選ぶことが大切です。
- チーム医療体制: 医師だけでなく、看護師や介護士など、多職種が連携して患者をサポートするチーム医療体制が整っている医療機関を選ぶことも重要です。 チーム医療では、患者へのより包括的なケアが期待できます。
- 病院の雰囲気: 実際に病院を訪れて、雰囲気を確認することも大切です。 清潔感があり、患者が安心して過ごせるような雰囲気の病院を選ぶことが重要です。
3. インテリアと心のケア
医療機関選びだけでなく、ご自宅のインテリアも、母の精神状態に影響を与える可能性があります。 落ち着いて過ごせる空間づくりを心がけましょう。
ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)
- 落ち着いた色合いのインテリア: グレーやベージュなどの落ち着いた色合いのインテリアは、リラックス効果があります。 刺激の少ない、穏やかな空間づくりを心がけましょう。
- 自然光を取り入れる: 自然光は、心の安らぎを与えてくれます。 カーテンやブラインドなどを適切に調整し、自然光を効果的に取り入れましょう。
- 植物を置く: 観葉植物などを置くことで、空間の癒し効果を高めることができます。 ただし、手入れが簡単な植物を選びましょう。
- 思い出の品を飾る: 母の好きな写真や思い出の品を飾ることで、安心感を与え、心の安定につながる可能性があります。
4. 専門家のサポート
介護は一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
- ケアマネージャー: ケアマネージャーは、介護サービスの利用計画作成や調整など、介護に関する様々な相談に対応してくれます。
- 医師・看護師: 医療機関の医師や看護師に、母の症状や介護に関する相談をすることも重要です。
- 精神科医: 必要に応じて、精神科医に相談し、母の精神状態のケアについてアドバイスを求めることも有効です。
今回の経験は、決して無駄ではありません。 この経験を活かし、より良い医療環境を選び、母さんのケアを継続していくために、積極的に行動していきましょう。 そして、ご自身の心身も大切にしてください。