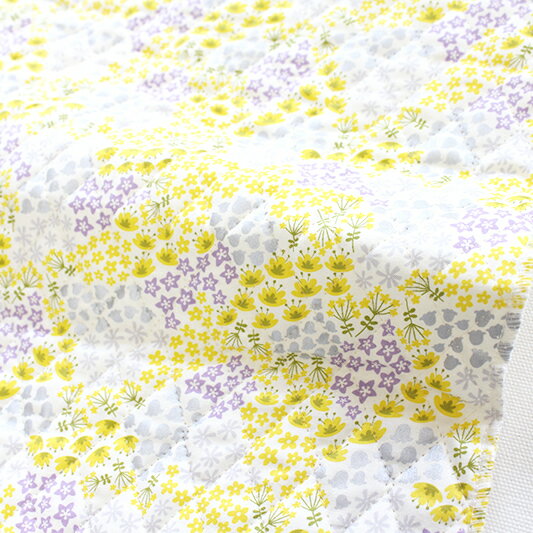要介護3の母を介護、夫婦と親子の関係では温度差があるのか?以前もこのカテで質問経験のある者です。母が要介護のなって以来、家の中がギクシャクしています。その原因は母の夫である父が自己中心的で、献身的な世話をしていないからです。父は昭和11年生で、76歳、定年以前は会社員生活が少なく、自営運送業、タクシー運転手など個人でする仕事に就いておりました。サラリーマン時代は ①職場の同僚と仕事上のことで口論になり、暴力を振るった。(すぐに配置転換) ②同じく上司に反抗し、会社を辞めるきっかけとなった。 ③町内のお寺でお酒の入った人と口論になり、手を上げ、ガラスを破損した。 ④タクシー乗務でも『割の良い仕事』に当たらないとすぐに無線通信者に文句を言う。 ⑤勉強することが嫌いで地道なことを継続できない性格。 ⑥会社員時代は出世できず、直情径行、一言居士的な性格で組織、秩序、体制に馴染めず、我慢、辛抱が出来ない。 ⑦感情の起伏が激しく、腹に持つということ出来ず、すぐに表情に出し、言わないと気が済まないタチ。 ⑧人の上に立った事がないので、人を使うのが下手、気配りや根回しがなく、思いやりがない。以上の通りで、今、私の妻と父の関係が悪化しており、言葉を交わすことも少ないです。母の世話でこれまで妻が父に『こうしてあげたら』と助言してくれたのですが、行き違いから『構わんといてくれ』『放っといてくれ』と口走り、以来妻は、父に関わらないようにしており、コミュニケーションがありません。父に『自分一人で背負わず、みんなの協力が得られる』ように考え方、性格を改めるように長男の私がたしなめるのですが、聞く耳を持たず、私の子らも『おじいさんアホや、嫌いや』と相手にしていないようです。一番気の毒なのが母で、老後の末路がこのようになり、献身的に尽くそうとしないダンナでは可哀そうでなりません。父の世話は万事、自分の都合優先で『自分は嫌だけど母のためにしてやろう』という気が見えません。休日に母を入浴させていますが、先日の母の下半身を見ると、アザや擦り傷が目立っていました。父も普段、入浴させていますが、私と比べると時間が短く、頭の洗髪を殆どしてくれません。私は妻や子らに『おばあさんクサイ』と言われるのが辛く、そうならないように丁寧にしています。母はボケってしまっていますが、父より私との入浴を好みます。私は入浴中、ずっと母に『早口言葉』や『昔のこと』など話し、会話をするようにしているのですが、父の場合は話声など全くなく、聞こえて来るのは父の怒鳴り声ばかりです。母が転倒すると父は『大丈夫か』『どこが痛む』ではなく、『アホ、しっかり歩け』『モタタするな』『見てないからや』と怒ります。病人になっているのに、冷たい言葉ばかりで、優しい労りの言葉がありません。私や妻が居る前では、いやらしいほど見え見えの優しい振る舞いスタンドプレーをします。介護状態になったとは言え、私は母に『育ててもらった』『大きくしてもらった』感謝の気持ちを持っています。お風呂で母の大便を手にかけられても怒らないようにしています。トイレでお尻も拭いています。寒くても車椅子で散歩に回ります。洗濯も毎朝しています。手すりを付けたり、介護用品を買ったり作ったり、殆どしました。でも父は『すまんな』『ありがとう』『よくしてくれた』の言葉がありません。『要らないもの買うな』と言われたこともあります。53年間、夫婦続けている割に、母への愛情、思いやり、いたわりの態度が見えません。父は次男で早くに家を出ているのであまり自分の母親と過ごす時間は短かったと思います。時折、母に『こいつは良くやってくれた』『頑張ってくれた』と褒めるのですが、そう思うなら、もっと尽くしたれヨと思います。私は52歳ですが、76歳の父に同じことを要求しませんが、家に籠り、部屋でテレビを観ていて母を横に寝かせているだけの世話はして欲しくないと感じます。これらを面と向かって言うと父とケンカになります。若い者の言葉に耳を貸しません。病院にも月1回言ってますが、母一人、診察室に行かせ、自分は診察室にずっと居らず、喫茶コーナーで時間を潰しています。近隣の人からも『気難しい人』のイメージを持たれています。母が要介護になってから、地域や近隣の行事、付き合いに殆ど父は出なくなりました。自分で世間を狭めているようです。こんな父に一言忠告してくれる人が居ればよいですが、そんな人が見当たりません。昭和10年世代(戦前生まれ)の人ってみんなこんな考え方なのでしょうか?母に対する気持ちが母と親子関係にある私と思いは同じとしても、行動に温度差があります。会社の同僚も『昔の人は今のような考え方が出来ない』といっておりました。父も根は悪い人間ではないのですが、母が要介護になり、怒りぽっくなりました。
高齢者の介護と家族関係の課題:世代間のギャップとコミュニケーション不足
ご質問からは、要介護3の母親に対する父親の介護への関与の低さ、そしてそのことによる家族間の摩擦が強く感じられます。 これは、高齢化社会における普遍的な課題であり、世代間の価値観の違いやコミュニケーションの不足が大きく影響していると考えられます。父親の昭和11年生まれという世代背景も、その行動パターンを理解する上で重要な要素となります。
昭和世代の価値観と現代社会のギャップ
父親の経歴や性格から、自己中心的で、感情表現が直接的で、協調性に欠ける傾向があることが分かります。これは、昭和初期の厳しい社会環境の中で培われた生き方や価値観が、現代社会の協調性を重視する風潮と大きく食い違っているためと考えられます。 また、長年自営業に従事してきたことから、個人主義的な考え方が強く、他者への気配りや思いやりが不足している可能性があります。
コミュニケーションの難しさ:言葉にならない思い
父親は、言葉で感謝や愛情を表現することに慣れていない可能性があります。昭和世代は、感情を直接的に表現することを良しとしない傾向があり、行動で示すことを重視する傾向があります。しかし、その行動が、現代の価値観では理解されにくい、あるいは誤解を生む可能性があります。 妻や子供たちが父親の行動を「愛情がない」と受け取ってしまうのは、このコミュニケーションのずれが原因の一つと考えられます。
具体的な解決策:家族会議と環境整備
現状打開のためには、以下の具体的な対策が考えられます。
ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)
1. 家族会議の実施:それぞれの気持ちを共有する
まず、家族全員で話し合う場を設けることが重要です。それぞれの気持ちを率直に伝え、誤解を解き、共通の目標を定めることが必要です。この際、専門家の介入も検討しましょう。介護支援専門員や臨床心理士などの専門家は、家族間のコミュニケーションを円滑にするためのサポートをしてくれます。
2. 父親への働きかけ:具体的な役割分担と感謝の言葉
父親に直接的に「もっと手伝って」と言うのではなく、具体的な役割分担を提案し、その役割を果たしてくれた際には、感謝の気持ちを伝えることが大切です。例えば、「お父さん、今日は母の着替えを手伝ってくれると助かります」のように、具体的な指示を出すことで、父親の行動を促すことができます。また、感謝の言葉を伝える際には、「ありがとう。おかげで助かりました」と、具体的な行動に対する感謝を伝えるようにしましょう。
3. 環境整備:介護しやすい住環境を作る
住環境の整備も重要です。手すりの設置、段差の解消、介護用品の導入など、安全で快適な生活空間を作ることで、介護負担を軽減し、父親の負担感を減らすことができます。 特に、浴室は滑り止めマットや手すりの設置など、安全対策を徹底しましょう。 浴室の照明も明るくし、清潔感を保つことで、気持ちよく介護ができる環境を作ることができます。
4. グレーインテリアによる癒やしの空間づくり
グレーは、落ち着きと安らぎを与えてくれる色です。 ご家庭のインテリアにグレーを取り入れることで、家族のストレスを軽減し、穏やかな雰囲気を演出することができます。 例えば、壁や床にグレー系の壁紙や床材を使用したり、グレーの家具やファブリックを取り入れることで、リラックスできる空間を作ることができます。 グレーは、他の色との組み合わせも容易で、様々なインテリアスタイルに合わせることができます。 例えば、白やベージュと組み合わせることで、明るく清潔感のある空間を演出できます。また、木目調の家具と組み合わせることで、温かみのある空間を演出できます。 グレーインテリアは、高齢者にとって優しい空間を提供し、介護する側にも精神的な負担軽減に繋がります。
5. 専門家への相談:介護サービスの利用
介護サービスの利用も検討しましょう。訪問介護やデイサービスなどを利用することで、介護負担を軽減し、家族の時間を確保することができます。 また、介護に関する相談窓口も活用しましょう。地域包括支援センターや介護保険相談窓口では、介護に関する様々な相談に対応してくれます。
まとめ:家族の絆を取り戻すために
要介護者の介護は、家族にとって大きな負担となります。しかし、家族間のコミュニケーションを改善し、協力体制を築くことで、困難を乗り越えることができます。 今回のケースでは、父親の性格や世代間のギャップを理解した上で、具体的な行動計画を立て、専門家の力を借りながら、一歩ずつ解決に向けて進んでいくことが重要です。 グレーインテリアによる空間づくりも、その過程をサポートする一つの要素となるでしょう。