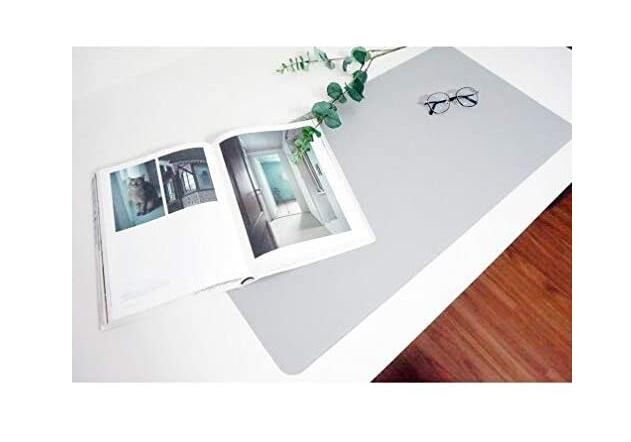Contents
早産と脳性麻痺、そして子育ての現実
ご質問の内容は、24週の早産、脳室側室周囲軟化症による脳性麻痺、そしてその後の育児における困難を訴える、非常に切実なものです。まず、ご自身の経験を詳細に語っていただき、ありがとうございます。 このような状況下での育児は想像を絶する苦労があることと思います。 一つずつ、問題点を整理し、解決策を探っていきましょう。
早産と医療体制の問題点
24週での破水、28週での出産、そして出産時の対応について、ご不満を感じている点がいくつかあります。
* 医師・助産師の対応:帝王切開の準備中に医師・助産師が不在となり、適切な対応が遅れたと感じている点。ナースコールにも対応が遅れた点。これは、医療現場の負担増加や人員不足といった問題が背景にある可能性があります。しかし、どのような状況であっても、患者さんへの適切な対応は最優先事項であるべきです。
* 出産時の状況:ベッド上での急な出産、そして新生児のNICUへの迅速な搬送。これは緊急性の高い状況であったことは理解できますが、親御さんへの情報提供が不足していた点が問題です。性別すら伝えられず、対面が半日以上遅れたことは、精神的な負担が大きかったでしょう。
ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)
これらの点は、医療機関への苦情として申し立てることも可能です。医療ミスに該当するかどうかは専門家の判断が必要ですが、記録や証言を元に、医療機関に改善を求めることも検討してください。医療相談窓口や弁護士への相談も有効です。
脳性麻痺と子育て支援制度
脳性麻痺と診断され、身体障害者手帳1級を取得されているとのこと。これは、お子さんの発達に合わせた支援が必要であることを示しています。
* 身体障害者手帳1級:この手帳は、様々な支援制度の利用を可能にします。具体的には、以下の支援が受けられます。
- 医療費助成:多くの自治体で、医療費の自己負担額が軽減されます。
- 介護保険サービス:お子さんの年齢や状態によっては、介護保険サービスの利用も可能です。ヘルパー派遣やデイサービスなどを利用することで、育児の負担を軽減できます。
- 障害児福祉サービス:保育所や療育施設の利用、訪問介護、相談支援など、様々なサービスが利用できます。自治体の障害福祉課に相談することで、最適なサービスを見つけることができます。
- 児童手当:障害児加算が支給されます。
- 特別児童扶養手当:お子さんの障害の程度に応じて支給されます。
* 小児科医の対応:小児科医から嫌な顔をされたとのことですが、これは適切な対応ではありません。医師には、患者さんに対して誠実で丁寧な対応が求められます。他の小児科医を受診することも検討してください。
具体的なアドバイス
* 自治体の相談窓口:まずは、お住まいの自治体の障害福祉課、子育て支援課などに相談しましょう。各制度の利用条件や申請方法、その他必要な支援について、丁寧に説明を受けられます。
* 専門機関への相談:地域の療育センターや発達相談機関などに相談することで、お子さんの発達状況に応じた適切な支援策を検討できます。
* 親のサポート:育児は一人で抱え込まず、周りの人に助けを求めることが大切です。ご家族や友人、地域の支援団体などに相談し、育児の負担を軽減しましょう。
* 記録の保持:医療機関とのやり取り、受診記録、各種申請書類などは、大切に保管しておきましょう。将来、何かあった際に役立ちます。
* 経済的な支援:経済的な負担が大きい場合は、福祉事務所などに相談し、生活保護などの制度の利用も検討しましょう。
まとめ
早産や脳性麻痺といった困難な状況の中、懸命に子育てをされていることに、心から敬意を表します。 制度の利用は複雑で、手続きも煩雑な場合があります。しかし、諦めずに、積極的に相談し、必要な支援を受けてください。 あなたと、そしてお子さんの未来のために、できる限りのサポートを受け、笑顔あふれる日々を送れるよう願っています。 この経験を活かし、同じような状況にある方々への支援に繋がる活動も検討してみてはいかがでしょうか。