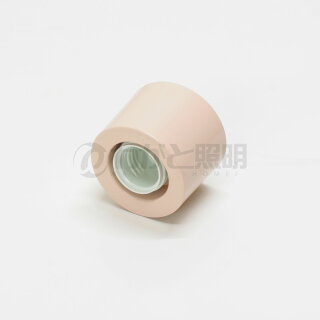Contents
ロフトの床面積算入について
建物の登記において、ロフトの床面積を算入するかどうかは、そのロフトの構造や利用状況によって判断されます。質問にあるように、天井高が2メートル(建築確認書では1.4m)あり、階段がない部屋の場合、登記上の扱いは複雑です。単純に天井高だけで判断できるものではなく、以下の点を総合的に検討する必要があります。
1. 天井高
建築基準法では、天井高が1.4m以上の部分を「小屋裏」と定義しています。しかし、登記においては、天井高だけでなく、居住性や利用状況も考慮されます。質問のロフトは天井高2mと、小屋裏の基準を大きく上回っています。これは、床面積算入の可能性を高めます。
2. 階段の有無
階段がない点が重要なポイントです。階段がないということは、日常的に利用しにくい空間である可能性が高いことを示唆します。そのため、床面積に算入しない可能性も考えられます。しかし、仮にハシゴ等でアクセス可能であれば、居住空間として利用できる可能性があり、算入される可能性も否定できません。
3. 利用状況
ロフトがどのように利用されているか(居住空間、収納空間、その他)も重要な判断材料となります。居住空間として利用されている場合、床面積に算入される可能性が高いです。一方、単なる収納空間として利用されている場合は、算入されない可能性があります。写真や図面があれば、判断材料として役立ちます。
4. 建築確認書との相違点
建築確認書に記載されている天井高と実際の天井高に相違がある点も問題です。これは、建築確認申請時の誤りや、後から改修された可能性を示唆しています。この点については、建築確認済証や設計図書などを確認し、状況を明確にする必要があります。
登記申請書への階数の記載
ロフトの床面積算入の可否と同様に、階数の記載も明確な基準がありません。一般的には、人が普通に生活できる空間として利用できる階層を数えます。
* ロフトが居住空間として利用され、床面積に算入される場合、そのロフトを別階として記載する可能性があります。
* ロフトが居住空間として利用されない場合、階数には含めない可能性が高いです。
専門家への相談
上記のように、ロフトの床面積算入と階数の記載は、ケースバイケースで判断が異なります。土地家屋調査士や司法書士といった専門家に相談することが最も確実な方法です。彼らは登記に関する豊富な知識と経験を持っており、状況を的確に判断し、適切なアドバイスをしてくれます。
専門家への相談のメリット
* 正確な判断:専門家は、法令や判例に基づいて正確な判断を行います。
* 適切な手続き:登記申請に必要な書類や手続きを適切にアドバイスします。
* トラブル回避:誤った手続きによるトラブルを回避できます。
具体的な行動ステップ
1. **写真・図面の準備:** ロフトの状況が分かる写真や図面を準備します。天井高、階段の有無、利用状況などが分かるように撮影しましょう。
2. **関係書類の確認:** 建築確認済証、設計図書、測量図など、関連する書類を全て確認します。
3. **専門家への相談:** 土地家屋調査士または司法書士に相談し、状況を説明してアドバイスを求めます。複数の専門家に相談し、意見を比較検討することも有効です。
4. **登記申請書類の作成:** 専門家のアドバイスに基づいて、登記申請書類を作成します。
5. **登記申請:** 作成した書類を法務局に提出します。
まとめ
ロフトの床面積算入と階数の記載は、天井高、階段の有無、利用状況など複数の要素を総合的に判断する必要があります。専門家のアドバイスを得ながら、正確な手続きを進めることが重要です。自己判断で進めることで、後々トラブルに発展する可能性もありますので、必ず専門家の意見を聞きましょう。