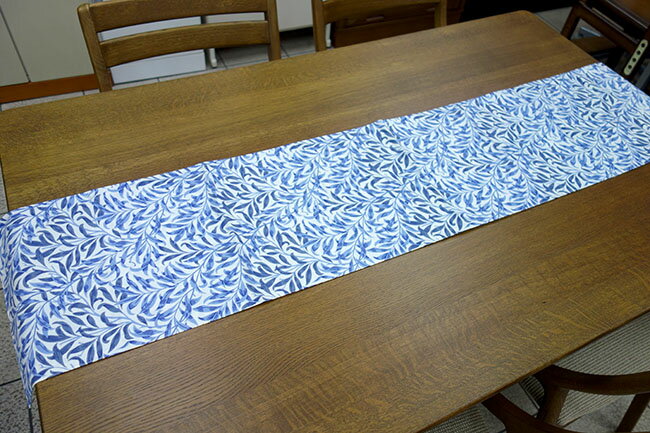Contents
新築店舗住宅の経費按分:確定申告における注意点
確定申告が迫り、新築店舗住宅の経費按分に頭を悩ませているとのこと、大変お困りのことと思います。ご質問にあるように、整体院(事業所得)と賃貸(不動産所得)を併用する店舗住宅の経費は、それぞれの所得に按分して計上する必要があります。国税庁からの回答通り、単純に「按分する」だけでは不十分で、具体的な按分方法と、それぞれの帳簿への適切な記載方法を理解する必要があります。
経費按分の考え方と具体的な方法
まず、土地取得費用、建物建築費用、駐車場工事費用など、全ての費用を事業用部分と賃貸用部分に按分する必要があります。これは、面積比率、使用比率、収益比率など、複数の要素を考慮して行うのが一般的です。
面積比率による按分
最もシンプルな方法は面積比率です。建物全体の面積に対して、整体院に使用している面積(1階部分の1/2)と賃貸に使用している面積(残りの部分)の比率で按分します。例えば、建物全体の面積が100㎡で、整体院が50㎡、賃貸が50㎡であれば、費用はそれぞれ50%ずつ按分されます。
使用比率による按分
面積比率だけでは不十分な場合もあります。例えば、駐車場が店舗用としてのみ使用されている場合は、駐車場費用は全て事業所得に計上するのが適切です。また、共用部分(廊下、階段など)についても、使用状況に応じて按分する必要があります。
ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)
収益比率による按分
収益比率は、それぞれの用途から得られる収益の比率で按分する方法です。整体院の売上高と賃貸収入を比較し、その比率で費用を按分します。この方法は、それぞれの用途の収益性が大きく異なる場合に有効です。
複合的な按分方法
多くの場合、面積比率、使用比率、収益比率を組み合わせた複合的な按分方法が用いられます。どの比率を重視するかは、個々の状況によって異なります。税理士などの専門家に相談し、最適な按分方法を選択することが重要です。
それぞれの帳簿への記載方法
按分された経費は、それぞれの所得の帳簿に記載します。
① 整体院(事業所得)の帳簿
建物、土地、駐車場の費用を面積比率や使用比率で按分した金額を、減価償却費として計上します。
例:建物の取得費用が1000万円で、事業用部分が50%であれば、減価償却対象額は500万円となります。これを耐用年数に従って減価償却します。
* 減価償却費:50万円(例)
* 建物:500万円(減価償却対象額)
② 賃貸(不動産所得)の帳簿
同様に、建物、土地、駐車場の費用を按分した金額を、減価償却費として計上します。
例:建物の取得費用が1000万円で、賃貸用部分が50%であれば、減価償却対象額は500万円となります。これを耐用年数に従って減価償却します。
* 減価償却費:50万円(例)
* 建物:500万円(減価償却対象額)
重要な点:不動産所得の帳簿には、建物が資産として計上され、その減価償却費が計算されます。減価償却費は、建物の取得費用を耐用年数で割って計算されるため、減価償却対象額が明確に記載されている必要があります。
補足:減価償却費の借方と貸方
ご質問にある「事業主が減価償却費を借りる」という表現は、会計用語としては正確ではありません。減価償却費は、費用の計上であり、貸借対照表の資産ではなく、損益計算書の費用として計上されます。借方は費用勘定、貸方は減価償却累計額となります。
専門家への相談
確定申告は複雑な手続きであり、誤った計上は税務調査のリスクにつながります。今回のケースのように、事業と不動産の両方を兼ね備えた場合、正確な按分と計上は特に重要です。税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。
まとめ
新築店舗住宅の経費按分は、面積比率、使用比率、収益比率などを考慮して行う必要があります。それぞれの所得に適切に按分し、それぞれの帳簿に正確に記載することが重要です。確定申告期限が迫っている状況ですので、税理士などの専門家にご相談の上、正確な申告を行うようにしてください。