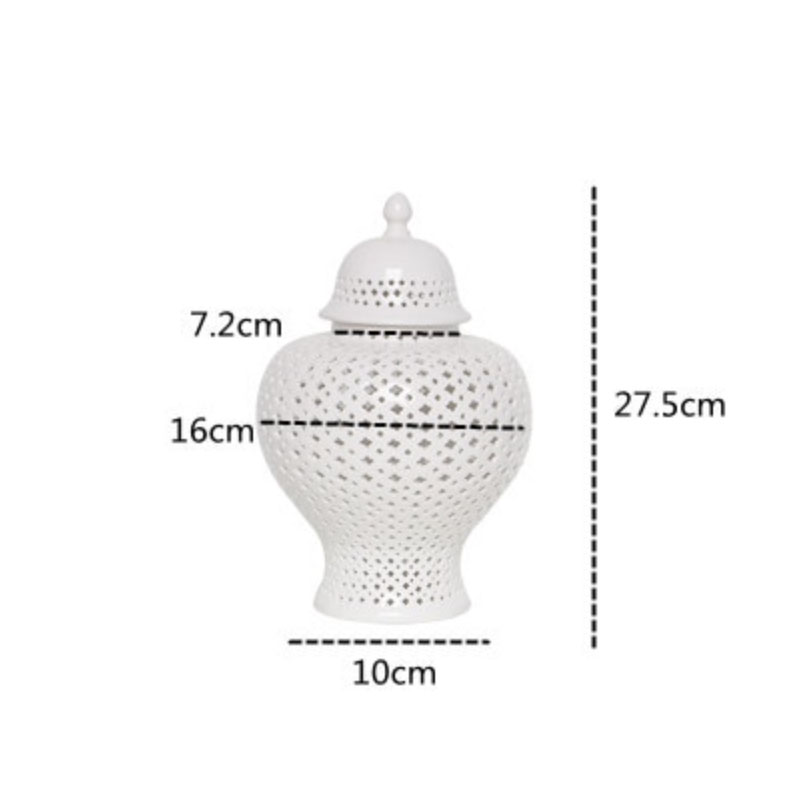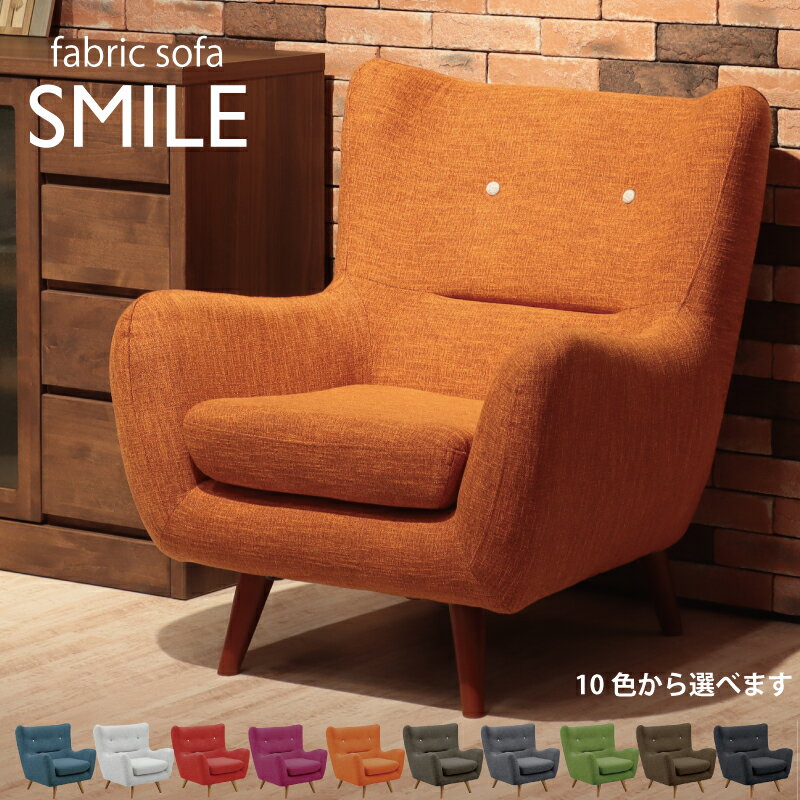Contents
新築住宅の揺れの原因:可能性を探る
新築住宅で感じる「ブルンブルン」という小刻みな揺れは、非常に不安な状況ですね。原因を特定するために、いくつかの可能性を検討してみましょう。ご質問いただいた内容から、以下の点を詳しく見ていきます。
1. 高速道路・地下鉄・道路交通の影響
高速道路から200m、地下鉄から400m、そして車通りの激しい道路から80mの距離にあるとのこと。 200m離れた高速道路の高架橋の影響を心配されていますが、高速道路の振動は、通常、そこまで離れた場所では感じにくいものです。周囲の建物が振動を吸収している可能性が高いです。同様に、地下鉄の振動も400m離れていれば、直接的な影響は少ないと考えられます。80mの道路も、車が通っていない時にも揺れを感じるという点から、直接的な原因とは言い切れません。
2. 地盤と基礎の問題
地盤の状況は非常に重要です。盛り土されていること、吹き抜けがあること、そして風通しの良い立地であることは、揺れに影響を与える可能性があります。
* 盛り土:盛り土は、地盤の沈下や不同沈下を引き起こす可能性があり、建物の揺れにつながる場合があります。特に、斜めスロープ状の駐車場が作られていることから、地盤の安定性に懸念が残ります。
* 吹き抜け:吹き抜けは、建物の剛性を下げる可能性があります。風による揺れを増幅させる可能性も考えられます。
* 風通しの良い立地:風当たりが良いということは、風の影響を受けやすいということです。特に高さが周囲より高い場合、風の影響を受けやすくなります。
ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)
べた基礎は、一般的に地盤の弱い場所でも安定性を高める効果がありますが、地盤調査が不十分であったり、施工に問題があったりすると、効果が期待できない場合があります。建築時の地盤調査報告書を確認し、地盤の状態と基礎の設計が適切であったかを確認することが重要です。
3. 建物の構造と窓面積
南向きの南北に長い長方形の建物で、片側の窓面積が広いとのこと。これは、風の影響を受けやすい構造と言えるでしょう。特に、高さが周囲より高い場合、風の影響で揺れを感じやすくなります。
4. その他の可能性
* 近隣の工事:近隣で地盤改良工事や杭打ち工事など、振動を発生させる工事が行われている可能性はありませんか?
* 内部要因:床鳴りも指摘されていますが、建材の共振や、設備機器の振動が原因となっている可能性も考えられます。
* 心理的な要因:揺れを感じやすい体質や、不安から揺れを過剰に感じている可能性も否定できません。
揺れの原因特定と対策
揺れの原因特定には、専門家の助けが必要となるでしょう。
1. 専門家への相談
まず、建築会社に相談することが重要です。建築会社は、設計図や施工記録を元に、原因を特定する上で役立つ情報を持っています。また、建築士や構造設計士に相談し、建物の構造的な問題がないか確認してもらうことも有効です。さらに、地盤工学の専門家に地盤調査の結果と現在の状況を評価してもらうのも良いでしょう。
2. 揺れの計測
専門家は、建物の揺れを計測する機器を用いて、揺れの頻度や強さを測定します。これにより、揺れの原因を特定する上で重要なデータが得られます。
3. 対策
原因が特定された後、適切な対策が講じられます。例えば、
* 地盤改良:地盤が不安定な場合は、地盤改良工事が必要となる場合があります。
* 建物の補強:建物の構造に問題がある場合は、補強工事が必要となる場合があります。
* 防振対策:防振ゴムなどの防振材を設置することで、振動を軽減することが可能です。
* 心理療法:もし、心理的な要因が影響している場合は、専門家によるカウンセリングを受けることを検討しましょう。
具体的なアドバイス
* **建築会社に連絡:** まずは建築会社に連絡し、状況を説明しましょう。保証期間内であれば、対応してもらえる可能性があります。
* **地盤調査報告書を確認:** 建築時に作成された地盤調査報告書を確認し、地盤の状況と基礎の設計を確認しましょう。
* **揺れの記録:** 揺れの発生日時、時間、強さなどを記録しておきましょう。これは専門家への相談時に役立ちます。
* **動画撮影:** 揺れている様子を動画で撮影しておくと、専門家への説明が容易になります。
* **近隣への聞き込み:** 近隣住民に同様の揺れを感じている人がいないか聞いてみましょう。
まとめ
新築住宅の揺れは、非常に深刻な問題です。原因を特定し、適切な対策を講じることで、安心して暮らせる環境を取り戻しましょう。専門家の力を借りながら、問題解決に向けて積極的に行動することが大切です。