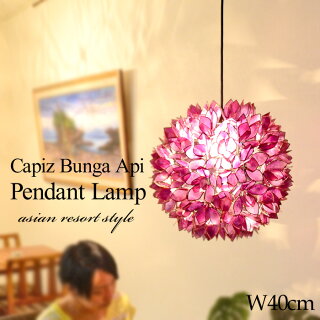Contents
新築なのに結露が酷い…その原因と対策
新築マンションの端部屋で、窓だけでなく外壁にも激しい結露が発生しているとのこと、大変お困りのことと思います。19℃の暖房で換気もしているにも関わらず、水たまりができるほどの結露は、確かに異常です。原因を特定し、適切な対策を行うことが重要です。
結露の原因を徹底的に探る
結露は、空気中の水分が冷たい物体に触れて水滴になる現象です。今回のケースでは、外壁と窓が特に冷えていることが原因と考えられます。しかし、なぜここまで激しい結露が発生するのでしょうか?いくつかの可能性を検討してみましょう。
- 外壁の断熱性能不足:最も可能性が高いのは、外壁の断熱材が不足している、もしくは施工不良であることです。特に端部屋は、外気に直接触れる面積が大きいため、断熱性能が低いと冷え込みが激しくなります。新築なのに…と不安に思われるのも無理はありません。建築会社に相談することが重要です。
- 窓の断熱性能不足:窓ガラス自体が断熱性能の低いものを使用している、もしくは窓枠からの隙間風がある可能性があります。窓の結露はよくあることですが、壁まで結露が酷い場合は、窓の問題だけでなく、他の要因も考えなければなりません。
- 換気不足:1日1回の換気では不十分な可能性があります。特に、結露が発生しやすい冬場は、こまめな換気が重要です。24時間換気システムが搭載されているか確認し、適切に機能しているか確認しましょう。また、換気扇の能力も確認しましょう。古い換気扇は換気能力が低下している可能性があります。
- 気密性の問題:建物の気密性が低いと、外気が室内に侵入しやすくなり、壁が冷えやすくなります。隙間風がないか、窓やドアの周りのシーリングを確認してみましょう。専門業者に依頼して気密測定を行うのも有効です。
- 生活習慣:加湿器は使用していないとのことですが、調理や洗濯、入浴などでも室内の湿度が上がります。これらの活動による湿度の影響も考慮する必要があります。ただし、今回のケースでは、水たまりができるほどなので、生活習慣だけで説明するのは難しいでしょう。
具体的な対策と専門家への相談
まずは、建築会社に連絡し、状況を説明することが重要です。新築であることから、施工不良の可能性も考慮し、早めの対応が必要です。建築会社は、原因調査を行い、適切な補修工事を行う責任があります。
建築会社への連絡と並行して、以下の対策も検討してみましょう。
- 窓の結露対策:窓に断熱シートを貼る、カーテンを厚手のものに変えるなどの対策で、窓の結露を軽減できます。ただし、壁の結露までは防げません。
- 除湿機の導入:空気中の水分を吸収する除湿機を使用することで、室内の湿度を下げ、結露の発生を抑えることができます。特に、冬場は効果的です。コンプレッサー式とデシカント式がありますが、冬場の低い温度でも効果を発揮するデシカント式がおすすめです。
- 換気方法の見直し:1日1回の換気だけでなく、こまめな換気を心がけましょう。窓を開けるのが難しい場合は、換気扇を積極的に使用しましょう。24時間換気システムの稼働状況も確認してください。
- 壁の断熱対策:壁に断熱材を追加することは、DIYでは困難です。建築会社に相談し、専門業者に依頼しましょう。内壁に断熱材を追加するリフォームも検討できます。
専門家の視点:建築士の意見
建築士の視点から見ると、新築で水たまりができるほどの結露は、断熱性能の不足が最も疑われます。特に端部屋は、外壁からの熱損失が大きいため、断熱材の厚みや種類、施工精度が重要になります。建築基準法では、最低限の断熱性能は規定されていますが、快適な室内環境を確保するためには、それ以上の性能が必要な場合もあります。
建築会社に相談する際には、以下の点を伝えましょう。
* 結露の状況(写真や動画があると効果的です)
* 部屋の温度と湿度
* 換気方法
* 外壁の温度
インテリアとの調和:結露対策とデザイン
結露対策は、インテリアにも影響を与えます。例えば、結露しやすい壁に、通気性の良い素材の家具を配置したり、壁掛けの飾り棚を避けるなどの工夫が必要です。また、除湿機や空気清浄機などの家電もインテリアの一部として、デザイン性も考慮して選びましょう。グレーの落ち着いた色合いの家電や家具は、どんなインテリアにも合わせやすくおすすめです。
まとめ:早めの対応が重要
新築マンションの激しい結露は、放置するとカビやダニの発生、健康被害につながる可能性があります。建築会社への連絡を最優先に行い、原因究明と適切な対策を実施しましょう。専門家のアドバイスを受けながら、快適な住環境を取り戻してください。