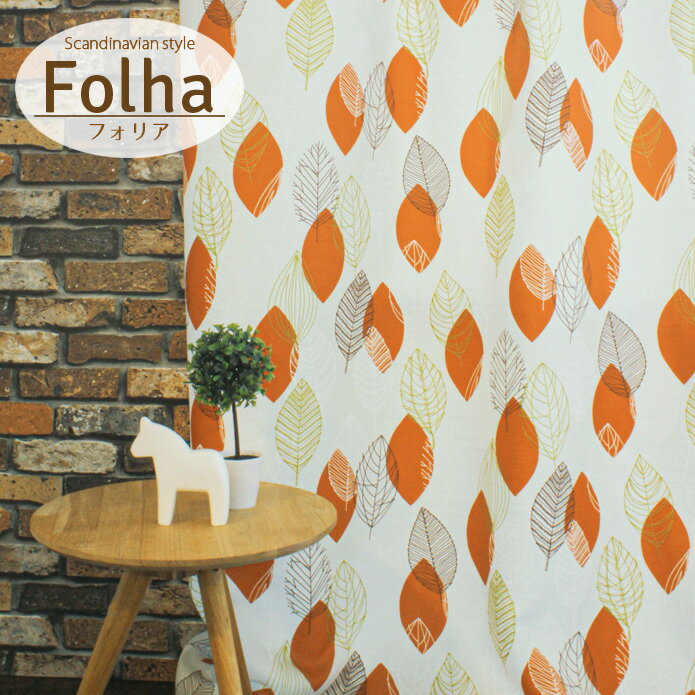Contents
愛犬の認知症(犬認知機能障害:CCD)とは?
愛犬の高齢化に伴い、心配になるのが「認知症」ではないでしょうか。正式には「犬認知機能障害(Canine Cognitive Dysfunction:CCD)」と呼ばれ、人間のアルツハイマー病と似た症状を示します。 15歳という年齢はシーズー犬にとって高齢期にあたり、CCDを発症する可能性は高くなります。 トイレができる、飼い主を認識するなど、症状は様々で、進行も個体差が大きいため、早期発見が大切です。
CCDの初期症状:あなたの愛犬は大丈夫?
ご質問にある症状は、CCDの初期症状として十分考えられます。具体的に見ていきましょう。
行動の変化
* 抱っこを嫌がるようになった: 以前は大好きだった抱っこを嫌がるようになったのは、触覚過敏や不安感の表れかもしれません。高齢犬は体の痛みや不快感を感じやすくなり、抱っこが負担になっている可能性があります。
* 落ち着きなく歩き回る: これは「徘徊」と呼ばれる症状で、CCDの代表的な兆候の一つです。場所の認識が曖昧になり、落ち着かない行動を取ることがあります。
* 玄関を見つめる: これは「見失い」という症状に関連している可能性があります。過去の記憶に囚われ、かつてよく通った場所や、家族が帰ってくるのを待ち続ける行動です。
これらの症状は、必ずしもCCDを示すものではありませんが、高齢犬においては注意深く観察する必要があります。 他の原因(痛み、聴覚・視覚の低下など)の可能性も考慮し、獣医師への相談が不可欠です。
ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)
CCDの進行と対処法
CCDは徐々に進行していく病気です。初期段階では、上記のような比較的軽微な症状が現れますが、進行すると、以下の様な症状が現れる可能性があります。
進行したCCDの症状
* 昼夜逆転: 夜に活動的になり、日中は眠っている時間が長くなる。
* 排泄の失敗: トイレを覚えているのに、場所を間違えたり、我慢できなくなったりする。
* 家の中で迷子になる: 以前はよく知っていた場所でも迷ってしまう。
* 攻撃性や不安の増大: 普段は穏やかな犬が、攻撃的になったり、過度に不安になったりする。
* 飼い主の認識の低下: 最終的には飼い主を認識できなくなるケースもある。
しかし、ご安心ください。 CCDは完全に治る病気ではありませんが、進行を遅らせ、愛犬の生活の質(QOL)を向上させるための治療やケアがあります。
具体的な対処法と獣医師との連携
愛犬の症状が気になる場合は、すぐに獣医師に相談しましょう。 獣医師は、身体検査や血液検査などを行い、CCDかどうかを診断します。 診断された場合、以下の様な治療やケアが提案される可能性があります。
獣医師による治療
* 薬物療法: 認知機能改善薬の投与により、症状の進行を遅らせる効果が期待できます。
* サプリメント: 脳の健康をサポートするサプリメントの投与。
飼い主さんによるケア
* 環境調整: 愛犬が安全で落ち着ける環境を作る。家具の配置を変えたり、滑りにくい床材を使用したりする。
* 規則正しい生活: 食事や散歩の時間を決めることで、愛犬のリズムを整える。
* 認知機能トレーニング: 簡単な訓練や遊びを通して、脳を活性化させる。
* ストレス軽減: 愛犬がリラックスできる環境を作る。優しく語りかけたり、撫でたりする。
* 食事療法: 脳の健康に良いとされる栄養素を含む食事を与える。
具体的な環境調整の例
* 夜間の照明: 夜間は薄暗い照明を点灯させて、愛犬が落ち着いて過ごせるようにする。
* トイレの場所: トイレの場所を分かりやすくする。
* 家具の配置: 家具の配置を固定し、愛犬が迷子にならないようにする。
専門家の視点:動物行動学者のアドバイス
動物行動学者によると、CCDの愛犬への接し方として、以下の点が重要です。
* 優しく、穏やかに接する: 焦らず、ゆっくりと、優しく接することが大切です。
* 無理強いしない: 愛犬が嫌がることを無理強いしない。
* 日常のルーティンを守る: 愛犬が安心できる日常のルーティンを守る。
* コミュニケーションを大切にする: 愛犬とコミュニケーションを取り、安心感を与える。
まとめ:愛犬との時間を大切に
CCDは悲しい病気ですが、適切なケアを行うことで、愛犬の生活の質を向上させることができます。 獣医師との連携を密にし、愛犬の症状に合わせた適切な治療やケアを行いましょう。 そして、何よりも大切なのは、愛犬との時間を大切に過ごすことです。 愛犬の小さな変化にも気づき、愛情をもって接することで、愛犬は安心し、幸せな時間を過ごすことができるでしょう。