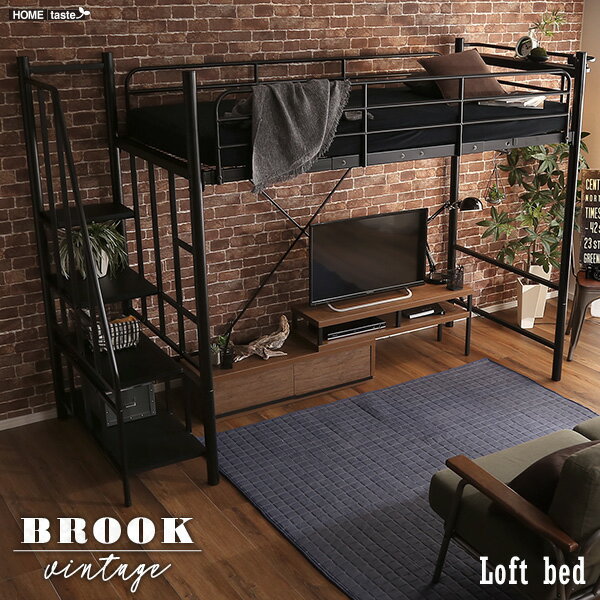Contents
プリントの山、60cmの壁を突破する方法!
学生生活は、授業やゼミ、サークル活動など、たくさんのプリント類が溢れがちですよね。 「後で役に立つかも…」と捨てられない気持ち、よく分かります。でも、60cmもの高さのプリントの山は、見た目にも圧迫感があり、勉強の集中力にも影響してしまいます。 そこで、今回は学生さん向けに、プリントの山を効率的に片付ける方法、そして、将来役立つ情報を残すための整理術をご紹介します。
1. プリントの選別:捨てる勇気と残す基準を明確に!
まずは、プリントの山と真正面から向き合いましょう。全てのプリントを一度テーブルなどに広げ、以下の基準で選別します。
- 絶対に必要なもの:試験範囲、重要な課題の資料、将来役立つ資格試験の参考資料など。これは、ファイルにきちんと整理して保管しましょう。
- もしかしたら必要かも…なもの:授業の補足資料、セミナー資料など。これは、一旦別の場所にまとめておき、1ヶ月後に見直してみましょう。1ヶ月経っても見なければ、ほぼ確実に不要です。思い切って処分しましょう。
- 完全に不要なもの:既に理解した内容のプリント、配布されただけで全く見ていないものなど。迷わず処分しましょう。
この選別作業は、一度に全て行う必要はありません。時間がない場合は、1時間だけ選別作業に時間を割くなど、少しずつ進めていくのがおすすめです。
2. デジタル化:スキャナーで効率的にデータ化!
重要なプリントは、デジタル化することで場所を取らず、検索も容易になります。スキャナーがあれば、簡単にデジタル化できます。スマホアプリでもスキャン機能が充実しているので、手軽に始められます。
- おすすめのスキャナー:予算や使用頻度に合わせて、フラットベッド型、シートフィード型など様々なタイプがあります。価格比較サイトなどを活用して、自分に合ったスキャナーを選びましょう。
- スマホアプリ活用:Evernote Scannable、Adobe Scanなどのアプリは、高画質で簡単にスキャンできます。OCR機能付きのアプリなら、テキストデータ化も可能です。
- クラウドサービスとの連携:Google Drive、Dropbox、OneDriveなどに保存すれば、パソコンやスマホからいつでもアクセスできます。
3. 収納方法:ファイル、バインダー、ボックスを活用!
デジタル化できないプリントや、厳選して残したプリントは、適切な収納方法を選びましょう。
- ファイル:A4サイズのファイルに、科目別に整理して収納します。クリアファイルを使うと、中身が見えて便利です。
- バインダー:複数の科目のプリントをまとめて収納できます。リフィルを追加すれば、容量を増やすことも可能です。
- ボックス:ファイルやバインダーをまとめて収納するのに便利です。ラベルを貼って、中身が分かるようにしておきましょう。
4. 定期的な見直し:溜めない習慣を身につける!
プリントを溜めないためには、定期的な見直しが必要です。例えば、学期末や長期休暇前に、不要なプリントを処分する習慣をつけましょう。
5. 専門家からのアドバイス:整理収納アドバイザーの視点
整理収納アドバイザーの視点から見ると、プリントの整理は「捨てる」という行為が重要です。 「後で使うかもしれない」という気持ちは、誰にでもあります。しかし、本当に必要なもの以外は、迷わず捨てる勇気を持つことが、スッキリとした空間を作る第一歩です。 また、捨てる際には、ゴミとして処分するだけでなく、古紙回収に出すなど、環境にも配慮しましょう。
6. 具体的な実践例:週1回の整理時間を確保!
例えば、毎週日曜日の夜に30分間、プリントの整理時間を確保してみましょう。その日のうちに新しいプリントを整理し、不要なものを処分することで、プリントの山が大きくなるのを防ぎます。
まとめ:青色のインテリアとプリント整理の意外な関係
青色は、集中力や生産性を高める効果があるとされています。勉強部屋に青色のインテリアを取り入れることで、整理整頓のモチベーションを高める効果も期待できます。例えば、青色のファイルボックスやペン立てを使う、壁に青色のポスターを貼るなど、小さな工夫から始めてみましょう。 プリント整理と並行して、青色のインテリアを取り入れて、より快適な学習環境を作ってみてください。