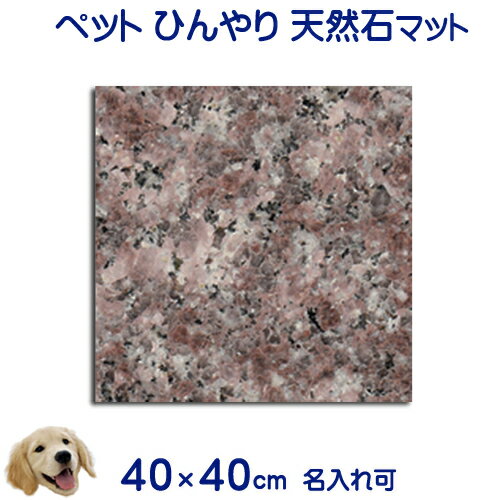子猫 保護 猫風邪 インターフェロン 脱水症状(1)で検索してみて下さい 15:00 18:00 水にお砂糖を溶いたものをシリンジで与えてみるが飲まない。あまり鳴かなくなった。昨日より元気がないようだ。体が少し熱を持っているように感じた。今日は病院が休みで明日連れて行こうと思った。少し毛が膨らませていて寝るより座っていることが多くなったように感じる。点眼の効果もこれ以上は回復が見られない。 21:00 ネットで思いつく限り病気について調べた。猫風邪と猫クラミジア、目は角膜潰瘍ではないかと思った。 22:30 食欲の無さはダニやノミからによるものではないかとも思い、先日病院で貰ったフロントラインを初めて極々少量をすることにした。残りは家の高齢猫にする。 バスタオルにホカロンを入れて子猫を置いてみる。(注意 温度がすぐに上がるためバスタオルでぐるぐる巻きしてください 子猫の皮膚に近いと命が危険です。脱水症状を伴います) 23:30 丸くなって寝ている。様子には変わりがない。 21日(祝) 24:30 ウンチをしたようだ。乾燥ウンチと少しだけど普通便があり採取してビニールに入れて明日病院へ持っていくように用意した。 子猫は変わりなく寝ている。 26:00 就寝する前にもう一度だけ子猫に見に行った。 横たわり伸びている?何か様子がおかしい。揺すってみた。 横たわりながら、足と手をバタつかせて目が見えてないのか意識がもうろうとしている すぐに抱き上げた。毛は湿って汗ばんでいる感じでぐったり。頭はだらんとなっている 私としたことがやってしまった。 ここからは、気が動転しながらも、思いつくことを試す。 砂糖水のシリンジを横たわった子猫に強制的に口に流しこむ。 ゴクク2口程飲んだ。 3口目、むせて吐き出す。 ハっハっと小刻みな発作が始まる 26:20 タクシーを調べて電話するが祝日の深夜、送迎車がつかまらない 自転車で駅のタクシー乗り場から高速で夜間動物病院へ 27:15 動物病院へ着いた時にはもう息がありませんでした。 処置はしてあげられなかった。 23日(水) 火葬してもらいお骨を抱いて帰宅しました。 手遅れながら家族として迎え名前をチビクロちゃんにしました。 私が殺めてしまった。繋ぐ命がこのような結果になり悔やまれてなりません。 本当に申し訳ないことをしました。 罪の無い子猫の人生を絶たせてしまった。 私の誤った自己判断による結果がこれでです。 一番恐れていたことが自らの落ち度で現実になりました。 なぜ、もっと調べて医師と相談しなかったのか。 免疫と細菌に戦うだけの体力は持ち合わせていなかったのだと思います 抗生物質やインターキャットの継続的な注射や栄養点滴も医師に相談すればよかったと思います。 ここ数日の外気温は28℃位でした。 曇り続きで数日はお風呂場でも比較的過ごしやすかったと思われますが 命が引き取る最後の日は30℃位はあったと思います。 一番の落ち度は、適切な環境を用意していなかった。 室内環境、室温を考えず、風呂場で通気の悪いダンボールで過ごさせてしまったこと。 脱水症状や熱中症になってしまったのだとも思います。 隔離するというのが前提で先住民の犬と猫の感染2次被害を恐れるがあまり 中途半端な状況しか考えられなかった。 子猫の伝染病よりも深刻に先に考えなければならなかったのは 体力と免疫の維持と向上でした。 そのためには適切な環境が整えなければならないということでした。 続き間のため冷房の冷気を隣の部屋まで送り、早急に大きめのゲージを買い 目の届くキッチンに置いて、体調を考えながら保温するか冷やすかを判断するべきでした。 通気性のあるゲージで、夏は涼しく、冬は暖かい場所で 塩素などの科学物質は、人間にしたら大したことなくとも 450グラムの小さい体の子猫には毒素を吸ったも同然でした。 絶対に避けるべきでした、気付くべきでした。 アパートの室内は気密性が高くこもりがちなので 熱中症になりかけていたのだとも思います。 冷やすべきでした。 ウンチが乾燥して便秘がちなら 自己排泄も容易じゃなかったと思います。 体力も消耗していったのだと思います。 脱水症状は少しづつ進んでいたんです なぜ気付かなかったのか、本当に馬鹿です この状況でカイロをして暖めることをしました。 数時間でダンボールの中の室温は30℃以上はあったのだと思います。 具合が悪いのにフロントラインをした あの子の残された時間は地獄だったと思います 保護どころか虐待に近い行為をしてしまいました。 ミルク飲まなくなった時点で脱水症状が進み命の危険があるのなら 動物病院へ連れて行く、獣医さんに見てもらう 1日様子を見る素人判断は急変するかもしれないないため手遅れになり危険です http://lovedog.mods.jp/sutenekowohirottara.htm http://www.lifeboatjapan.org/contents/baby_cats/?sub-nav http://tukichan.jp/b_contents/koneko/01.html補足知恵袋でも保護してから、最初は離乳のミルクを飲み始めるが途中から飲まなくなることが多いとのことですが それはどういう事が考えられますか? 風呂場(窓1箇所有り)
子猫の急死:悲劇から学ぶ、適切な保護とケア
この記事では、保護した子猫が急死したという悲しい出来事を通して、子猫の適切な保護方法、特に室内環境の重要性について学びます。 経験者の方の体験談を基に、具体的な対策と、獣医師のアドバイスも交えながら解説します。 早期発見と適切な対応の重要性を再認識し、同じ悲劇を繰り返さないために、ぜひ最後まで読んでください。
子猫の異変と対応:何が起こっていたのか
投稿者の方は、保護した子猫の異変に気づきながらも、適切な対応を遅らせてしまいました。 具体的には、以下の点が問題でした。
- 脱水症状の早期発見の遅れ:ミルクを飲まなくなり、元気がない、毛が膨らんでいるなどの症状が出ていたにも関わらず、すぐに動物病院へ連れて行かなかった。
- 不適切な保温:ホカロンを使用し、子猫を過剰に保温した。これは、既に熱中症気味だった子猫にとって、致命的な状況を招いた可能性が高い。
- 自己判断による治療:ネットの情報をもとに自己診断し、フロントラインを使用。子猫の体調を悪化させた可能性がある。
- 不適切な飼育環境:通気の悪い風呂場のダンボール内での飼育。高温多湿で、熱中症のリスクを高めていた。
- 動物病院受診の遅れ:祝日ということもあり、動物病院への受診が遅れたことも大きな要因。
これらの要因が重なり、子猫は容態を急激に悪化させ、残念ながら亡くなってしまいました。
子猫の保護:適切な環境とケア
子猫を保護する際には、以下の点に注意が必要です。
ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)
1. 適切な飼育環境の確保
- 温度管理:子猫は体温調節機能が未発達です。特に夏場は、直射日光を避け、エアコンなどで適切な室温(25~28℃程度)を保つことが重要です。冬場は、暖房で寒さを防ぎましょう。温度計で常に室温を確認する習慣をつけましょう。
- 通気性:通気性の良いケージを使用し、空気がこもらないように注意しましょう。ダンボールは通気性が悪く、高温になりやすいので避けるべきです。
- 清潔さ:ケージ内は常に清潔に保ち、定期的に清掃を行いましょう。排泄物の処理もこまめに行い、感染症予防に努めましょう。
- 安全な空間:子猫が安全に過ごせるように、危険な物や場所を避けましょう。高い場所や狭い場所へのアクセスを制限し、転倒や怪我を防ぎましょう。また、他のペットとの接触も注意深く管理しましょう。
- 隠れ家:子猫は不安を感じやすいので、落ち着ける隠れ家を用意してあげましょう。タオルや小さなハウスなどが役立ちます。
2. 健康管理と早期発見
- 定期的な健康チェック:毎日、子猫の様子を観察し、異変がないかを確認しましょう。食欲、排泄、活動量、呼吸、体温などに注意を払い、少しでも異変を感じたらすぐに動物病院へ連れて行きましょう。
- 脱水症状のサイン:元気がない、ぐったりしている、皮膚の弾力が低下している、口が乾いている、目や鼻が乾燥しているなどは、脱水症状のサインです。これらのサインに気づいたら、すぐに獣医師に相談しましょう。
- 獣医師への相談:子猫の健康状態について、獣医師に相談することをためらってはいけません。専門家のアドバイスを受けることで、適切なケアを行うことができます。
3. 栄養管理
- 適切なミルク:離乳前の猫には、子猫用のミルクを与えましょう。ミルクの量や頻度は、子猫の年齢や体重に合わせて調整する必要があります。獣医師に相談して適切なミルクを選び、与え方を学びましょう。
- 固形食への移行:離乳期には、徐々に固形食に移行していきます。最初は、子猫用のウェットフードを少量から与え始め、徐々に量を増やしていきます。フードの切り替えは、消化器系の負担を考慮し、徐々に進めることが重要です。
専門家の視点:獣医師からのアドバイス
獣医師によると、子猫の急死は、脱水症状、熱中症、そして不適切な環境が大きく影響している可能性が高いとのことです。 特に、高温多湿の環境下でのホカロンの使用は、子猫の体温を急激に上昇させ、熱中症を悪化させる危険性があります。 また、フロントラインなどの薬剤は、子猫の体への負担を考慮し、獣医師の指示に従って使用することが重要です。
まとめ:二度と繰り返さないために
今回の事例は、子猫の保護における適切な環境整備と健康管理の重要性を改めて示しています。 自己判断による治療や対応は危険であり、少しでも異変を感じたら、すぐに獣医師に相談することが大切です。 適切な環境とケアを提供することで、小さな命を守り、幸せな時間を共有できることを願っています。 この経験を教訓に、より多くの動物たちが安全で幸せな生活を送れるよう、私たち一人ひとりが意識を高めていくことが重要です。