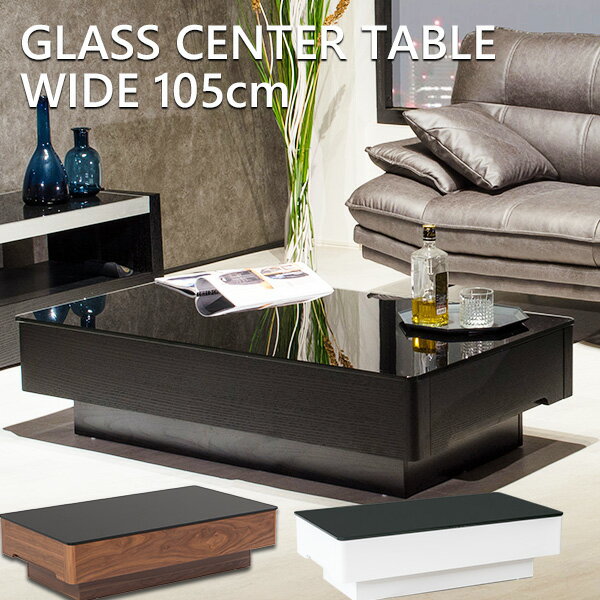任意売却物件取引における問題点と、契約継続の可否
ご質問の任意売却物件の取引は、非常に多くの問題点を抱えているように見えます。宅建協会の方が「異例中の異例」とおっしゃっている通り、通常の取引とは大きくかけ離れており、契約を継続することは非常に危険です。以下、各問題点について詳しく解説し、取引継続の可否についてアドバイスします。
問題点の詳細解説と、通常の取引との比較
① 契約書類の不足
通常、不動産売買契約においては、重要事項説明書、売買契約書、その他必要な書類が事前に交付されます。購買意志確認書のみで、その他の書類が一切ないのは極めて異例です。口頭やメールでのやり取りは、証拠が残りにくく、トラブル発生時のリスクが高まります。
② 契約日の変更と裁判所売却許可
契約日が変更になった理由が「裁判所の売却許可が下りない」というのは、非常に不自然です。任意売却において裁判所が関与するのは、債権者との合意が得られない場合など、特殊なケースに限られます。また、契約日の変更も、事前に書面で通知するのが一般的です。簡単に変更できるものではありません。住民票の提出についても、裁判所が絡んでいないのに提出を求められたのは、不審な点です。
③ 司法書士の選任
売主側が一方的に司法書士を選任している点も問題です。買主は、自分の信頼できる司法書士を選ぶ権利があります。不動産屋と司法書士が事前に繋がっている状況は、買主にとって不利な条件が設定される可能性があります。
ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)
④ 契約に必要な情報不足
契約に必要な書類、金額、その他重要な情報が提示されていないのは、重大な問題です。「早急にお知らせする」という曖昧な対応は、信頼性に欠けます。
⑤ 破産者の引っ越し
契約が確定していないのに破産者が引っ越ししているのは、非常に不自然です。物件の状況、債権者の意向などを考慮すると、何か隠された事情がある可能性が高いです。
⑥ 債権者と回収業者
第一抵当権者が住宅金融支援機構、債権回収業者がエムイーフロンティアという点も、取引の複雑さを示唆しています。複数の関係者が関与することで、情報が不透明になり、トラブルのリスクが増加します。
⑦ 鍵の引き渡し時期
契約終了後すぐに鍵が渡されるという点も、通常とは異なります。通常は、残代金の支払いが完了し、所有権移転登記が完了してから鍵が渡されます。
⑧ 不明確な説明
不動産屋の説明が曖昧で、具体的な情報が得られないのは、非常に危険なサインです。重要な事項について、はっきりとした説明がない場合は、契約を避けるべきです。
⑨ 住所確認の責任
物件の住所を自分で確認する必要があるというのは、不動産屋側の責任放棄です。不動産屋は、正確な住所情報を提供する義務があります。
⑩ 宅建協会の指摘
宅建協会が「通常ありえない取引」と指摘していることは、非常に深刻な問題です。何か不正が行われている可能性が高いと考えるべきです。
⑪ 不透明な関係
不動産屋、司法書士、債権回収業者の関係が不透明であることは、大きなリスクです。癒着や不正が行われている可能性も否定できません。
具体的なアドバイス:取引を継続すべきではない
上記の様々な問題点から判断すると、この取引を継続することは非常に危険です。 契約を進める前に、以下のことを強くお勧めします。
* **別の不動産会社に相談する**: 複数の不動産会社に相談し、今回の取引についてセカンドオピニオンを得ましょう。
* **弁護士に相談する**: 弁護士に相談し、法的観点からのアドバイスを受けることが重要です。契約書に署名する前に専門家の意見を聞くべきです。
* **契約をしない**: 現状では、契約を進めるべきではありません。リスクが高すぎるため、取引を中止することを強くお勧めします。
* **書面でのやり取りを徹底する**: 今後、不動産会社とやり取りをする際には、すべてのやり取りを文書で行い、証拠を残すようにしましょう。
通常の不動産売買契約の流れ
通常の不動産売買契約の流れは以下の通りです。
1. 物件探しと内見
2. 重要事項説明書の交付
3. 売買契約書の締結
4. 手付金の支払い
5. 残代金の支払い
6. 所有権移転登記
7. 鍵の引き渡し
今回の取引は、この流れから大きく逸脱しており、非常に不自然です。
まとめ
今回の取引は、多くの問題点があり、非常に危険です。 契約を継続することはお勧めできません。 専門家(弁護士、不動産会社)に相談し、適切な対応を取ることを強くお勧めします。 安全な取引を優先し、リスクを回避することが重要です。