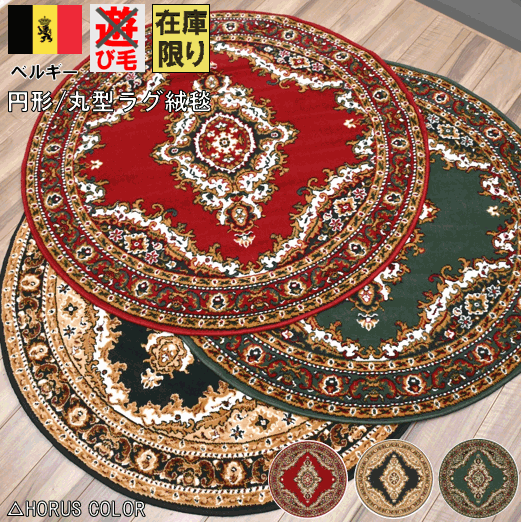Contents
問題点の整理:専有面積と建物使用面積の食い違い
8年前に契約したマンションの専有面積が不明確で、契約書には「建物使用面積」のみ記載されているという状況です。最近配布された他の部屋の販売チラシでは、専有面積と共有面積(ベランダ)の合計が、ご自身の契約書の「建物使用面積」と一致していることから、専有面積の食い違いが疑われています。 これは家賃計算に影響するため、正確な専有面積の確認が不可欠です。 さらに、高齢のオーナーとのコミュニケーションに難しさを感じている点も課題です。
解決策:正確な専有面積を調べるためのステップ
まずは、冷静に事実関係を整理し、段階的に解決策を探る必要があります。
1. 客観的な証拠の収集
* 販売チラシのコピーを複数枚確保する: 複数のチラシに同じ専有面積が記載されていることは、強い証拠となります。 日付や物件名などを確認し、記録として保管しましょう。
* 契約書の原本を確認する: 契約書に記載されている「建物使用面積」以外の情報(図面など)がないか、改めて確認します。 契約書に記載されている物件の住所や建物名なども確認しましょう。
* 管理会社への問い合わせ: マンションの管理会社に連絡し、建物の図面や過去の修繕履歴、各戸の専有面積に関する情報を求めます。 管理会社は建物の管理に関する情報を保有しているため、重要な情報源となります。
2. オーナーとのコミュニケーション方法の見直し
高齢のオーナーとのコミュニケーションは、慎重な対応が必要です。
* 書面でのやり取りを重視する: 電話でのやり取りは、誤解が生じやすいです。 内容証明郵便で、専有面積の確認を求める文書を送付することを検討しましょう。 内容証明郵便は、送付内容が確実に相手に届いたことを証明できるため、証拠として有効です。
* 具体的な質問を事前に準備する: 質問を明確に整理し、簡潔に質問することで、オーナーの負担を軽減できます。 例えば、「契約書に記載されている建物使用面積と、近隣物件の販売チラシに記載されている専有面積に差異があるため、正確な専有面積の確認を希望します。」のように、具体的な問題点を明確に伝えましょう。
* 第三者の介入を検討する: 状況によっては、弁護士や不動産仲介業者などの専門家に相談し、オーナーとの交渉を依頼することも有効です。 専門家は、法律的な観点から適切な対応をアドバイスし、交渉をサポートしてくれます。
3. 行政への相談
どうしても解決しない場合は、行政機関に相談することも可能です。
* 市区町村の建築指導課への相談: 建築に関する相談窓口として、市区町村の建築指導課があります。 建物の図面や登記簿などの情報について相談し、解決策を探ることができます。
* 消費者センターへの相談: 契約に関するトラブルであれば、消費者センターに相談することも可能です。 専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応を検討できます。
専門家の視点:不動産鑑定士の意見
不動産鑑定士は、不動産の価値を評価する専門家です。 専有面積の確認に迷う場合は、不動産鑑定士に相談することで、客観的な視点から解決策を提示してもらうことができます。 鑑定士は、建物の図面や登記簿などの資料を基に、正確な専有面積を算出することができます。 費用はかかりますが、正確な情報を得るためには有効な手段です。
具体的なアドバイス:行動計画
1. まずは、販売チラシのコピーを複数枚確保し、管理会社に連絡を取って建物の図面や各戸の専有面積に関する情報を求めます。
2. オーナーには、内容証明郵便で専有面積の確認を求める文書を送付します。 文書には、具体的な質問と、解決しない場合の対応(例えば、弁護士への相談)を明記しましょう。
3. 管理会社やオーナーからの回答がない場合、または回答に納得できない場合は、弁護士や不動産仲介業者、不動産鑑定士に相談します。
4. 最終手段として、市区町村の建築指導課や消費者センターに相談します。
まとめ:権利を主張し、解決を目指しましょう
チラシという客観的な証拠がある以上、正確な専有面積を知る権利はあなたにあります。 高齢のオーナーとのコミュニケーションには配慮が必要ですが、あなたの権利を主張し、冷静に解決策を探ることで、問題を解決できる可能性は十分にあります。 必要に応じて専門家の力を借りながら、積極的に行動を起こしましょう。