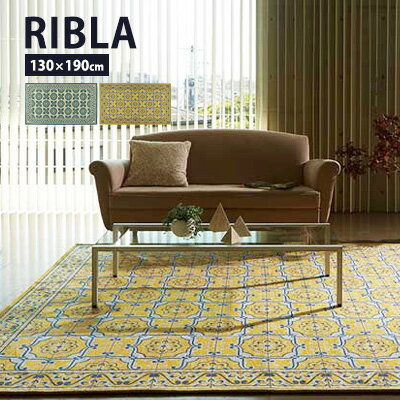Contents
トイレ跡地の10mmかさ上げ:簡単DIYで平らな床を実現
トイレ撤去後の排水口キャップによる10mmの段差、困りますよね。でも大丈夫!この記事では、110cm×85cmの狭い空間でも簡単にできる10mmかさ上げ方法と、クッションフロア施工のポイントを詳しく解説します。DIY初心者の方でも、写真付きで分かりやすく説明しますので、ぜひ最後まで読んで、快適な物置空間を手に入れてください。
1. かさ上げ材の選定:最適な素材と厚さ
10mmのかさ上げには、いくつかの素材が考えられます。それぞれのメリット・デメリットを比較して、最適な素材を選びましょう。
1-1. 合板
メリット:強度が高く、安定した仕上がりになる。比較的安価。
デメリット:厚さ10mmの合板は入手しにくい場合がある。カットが必要で、DIY経験がないと難しい。
1-2. 下地材(レベル調整材)
メリット:10mmの厚さのものが市販されている。施工が比較的簡単。
デメリット:合板に比べて強度が低い場合がある。広い面積には不向き。
ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)
1-3. セメント系ボード
メリット:強度があり、防水性も高い。
デメリット:重量があり、施工がやや難しい。10mmの厚さのものは入手しにくい。
今回のケースでは、10mm厚のレベル調整材が最も手軽でおすすめです。ホームセンターで簡単に購入できます。
2. 施工手順:10mmかさ上げDIYステップバイステップ
それでは、レベル調整材を使ったかさ上げ方法をステップバイステップで解説します。
2-1. 材料の準備
* 10mm厚のレベル調整材(110cm×85cmの面積に合わせて必要な枚数を計算)
* クッションフロア(110cm×85cmの面積に合わせて購入)
* 木工用ボンド
* ヘラ
* メジャー
* カッター
* ハサミ
* 養生テープ
2-2. 床の清掃
まず、作業前に床をしっかりと清掃します。ホコリや汚れがあると、接着剤がうまく付きません。
2-3. レベル調整材のカットと配置
レベル調整材を必要なサイズにカットします。カッターを使う場合は、定規などを当てて安全に作業しましょう。カットしたレベル調整材を、排水口キャップを覆うように配置します。
2-4. 木工用ボンドによる接着
レベル調整材の裏面に木工用ボンドを塗布し、床にしっかりと接着します。ヘラを使ってボンドを均一に広げると、より効果的です。
2-5. 重しによる固定
ボンドが乾くまで、レベル調整材の上に重しを乗せて固定します。数時間置いて、しっかり接着を確認しましょう。
2-6. クッションフロアの施工
ボンドが完全に乾燥したら、クッションフロアを施工します。クッションフロアの裏にボンドを塗布し、レベル調整材の上に丁寧に貼り付けます。ヘラを使って空気を抜くように貼り付けると、仕上がりが綺麗になります。
2-7. 余剰部分のカット
クッションフロアを貼ったら、余分な部分をカッターでカットします。
3. クッションフロアの選び方:デザインと機能性
クッションフロアは、デザインと機能性の両方を考慮して選びましょう。
3-1. デザイン
物置の雰囲気に合わせて、デザインを選びます。例えば、ベージュ系の落ち着いた色合いのクッションフロアは、どんなインテリアにも合わせやすくおすすめです。
3-2. 機能性
防水性や耐久性が高いクッションフロアを選ぶと、長く使えます。
4. 専門家からのアドバイス:DIYの注意点
DIYで床をリフォームする際には、以下の点に注意しましょう。
* 下地処理の重要性:床の清掃を徹底し、下地をしっかり乾燥させることで、接着剤の密着性を高め、剥がれを防ぎます。
* 適切な接着剤の使用:木工用ボンド以外にも、クッションフロア専用の接着剤を使用するとより確実です。
* 換気:作業中は十分な換気を心がけましょう。ボンドの臭いが気になる場合は、マスクを着用してください。
* 安全第一:カッターなどの刃物を使用する際は、十分に注意して作業しましょう。
5. まとめ:快適な物置空間をDIYで実現
今回の方法で、10mmの段差を解消し、快適な物置空間を作ることができます。DIYは、自分自身で空間を作り上げる喜びがあります。ぜひ、この記事を参考に、チャレンジしてみてください。